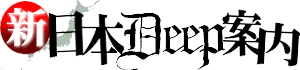県庁所在地の那覇から車であっちこっち回りながら北上してきて、ようやく本島北部最大の都市である名護市の街中までやってきた。ここまで来ると一般的な観光客は本部半島にある美ら海水族館だとか、最近橋が繋がって観光地化しだした古宇利島なんぞに行って「海が綺麗だね」なんて言って帰ってくるのだろうが、我々としては名護の街中を色々探索したい気持ちの方が大きい。

それでまず訪れたのは名護市役所庁舎。なんで市役所なんかに用事が…だなんて言葉はこの庁舎の珍建築っぷりを一目見ると分かるはずだ。まるでインドネシアかどっかの古代遺跡か寺院のようなイメージを連想させる。市役所の庁舎が、どうしてこうなった?!

庁舎の建物は言うなれば沖縄らしく穴あきブロック(花ブロック)を多用したコンクリート建築だが、夏の日差しのキツさや台風の猛烈さといった沖縄の気候を徹底的に考え意識的に風通しの良さを計算して建てられている。

庁舎の前の芝生広場から遠目に見ると独特の風情を感じられる。市役所の前にいる事すら忘れてしまいそうだ。なんだこの物凄い開放感は。

でもこんなでかいスローガン看板がデデーンと掲げられている所を見ると、やっぱりここは市役所なんだなと思う訳である。

建物自体にインパクトを持たせる為か通常の色に加えてピンク色のコンクリートブロックも使われていて、柱の部分は紅白のストライプになっている。これでも昔はもっと鮮やかなピンクだったのだが経年変化で少し黒ずんで、落ち着いた色合いに変わっているのだ。

積み上げられたコンクリートブロックに植物が絡まって上部で木陰を作っている。そこには沖縄らしくブーゲンビリアの花なんぞが咲いていて、見た目にもかなり涼しげな印象を与える。

この開放的過ぎる珍建築庁舎は1981年に作られている。大阪万博の時代に程近い「珍建築ブーム」とも言える時期のど真ん中、1971年に結成された建築家グループ「象設計集団(東京)」の手によって設計された。

この風通しの良すぎる建築設計が幸いし、建物完成後は長らくクーラーすら入れてなかったというのだから驚きだ。だが沖縄サミットのあった2001年頃に、パソコンなどの電子機器が増えだした為に室内温度が上昇し、遅まきながら空調設備を置くようになったとか。

屋根下に入っても全く圧迫感を感じる事がない。上層階にも植木なんかが置かれていたりして、極力自然の力で建物の熱を和らげるような取り組みをしているようだ。ちなみに屋上は見ていないが、一面屋上緑化の芝生が敷かれている。

屋根の部分もよく見ると穴の開いた部分に色つきガラスが嵌めこまれて、何やらメルヘンチックな演出を醸し出している。公的機関の建物と言えばバブル時代の悪趣味で豪華なハコモノばかりが目に付くが、そうしたものとは一線を画する、素敵な建築物だ。

外観だけ見てるとさすが物凄い建物だなあと思うのだが、ガラス戸を跨いだ建物内をちらりと見ると、そこはやはりフツーの地方自治体のお役所と変わらない。名護市は1970年に沖縄県下9番目の市として成立、現在の人口は約6万1500人。

市役所の正面入口はこっちだった。奇妙ながらも決して無駄を感じさせる事がない建物。綺麗事じゃないエコってこういう建物の事を言うんだろうな。まだ片側しか見ていないので、次は裏に回って見ることにする。

南国沖縄の強い夏の日差しにも負けないようにと穴あきブロックやら「アサギテラス」と呼ばれる階段状の独特な広いテラスに屋上緑化など様々な知恵を絞って作られた庁舎は築30年。木陰の下にいる限りは、暑さも和らぐ。

これでも30年前にヘンチクリンな庁舎が建てられた当時は賛否両論あったようだが、今ではすっかり街並みに溶け込んだ感がある。

今度はこの建物を裏側から眺めてみよう。国道58号に面する市役所の裏手はやはり同じように穴あきブロックが多用された妙に風通しの良さそうな外観をしている。が、表側と違うのが建物の柱に等間隔にシーサーが置かれている事。

しかもそのシーサーも一個一個手作りで全部姿形が違っている。全部で56体のシーサーが市役所庁舎に守り神として君臨している。このシーサー数の多さは世界一らしい。よくわからんけど。

屋上部分にまでまんべんなくシーサーが鎮座している。みんな個性的過ぎて、中には全然シーサーに見えずUMAみたいなのもいて意味不明。

牙を剥き出しにした男らしく獰猛なシーサーもいれば、女性っぽい仕草でお尻を突き出す可愛いシーサーさんもいる。いわゆるセクシーサー。

角度によってはなんだか恥ずかしいポーズに見えなくもないお尻突き出し系のセクシーサー2号。

さすがに56体全部を見て回るのは骨が折れる。この56という数字には意味があるらしく、名護市にある集落の数と、名護市役所を合わせた数が56なんだってさ。

それはそうと、これは…シーサーなのか?!

シーサーだらけの市役所庁舎の裏手には身障者用スロープで上まで行けるスペースがあって、この部分だけは大きく建物からはみ出て伸びている。30年前の建物にしては意外にバリアフリーも考慮されているんだね。

そんな名護市役所庁舎の真ん前の国道58号沿いに、アイスクリームの路上販売がいた。これも隠れた沖縄名物「ビックアイス」。本島北部の今帰仁村に本拠地があるらしく、この付近を車で走るとかなり高確率で発見出来るはずだ。

道端に唐突にパラソルを建てて営業しているスタイルは秋田のババヘラアイスと共通するが、売り子はババアではなく若い娘である。しかも高校生のアルバイト。概ねかったるそうな表情で、客の注文に応じてアイスクリームを盛りつけてくれる。

シャーベット状のビックアイス・シークワーサー味(1個150円)を沖縄の青空の下で食べる。こういう路上販売のアイスって何故だか旨い。っていうかオイシーサーって言っとくべきですかここは。